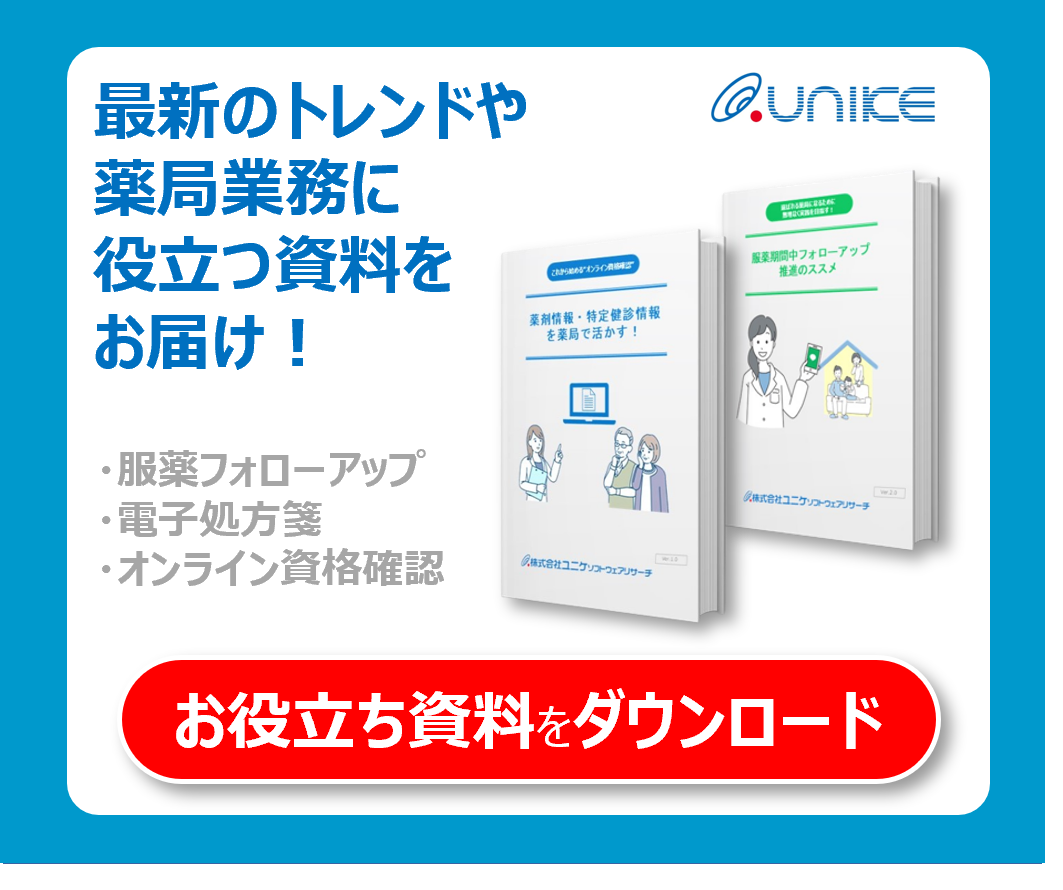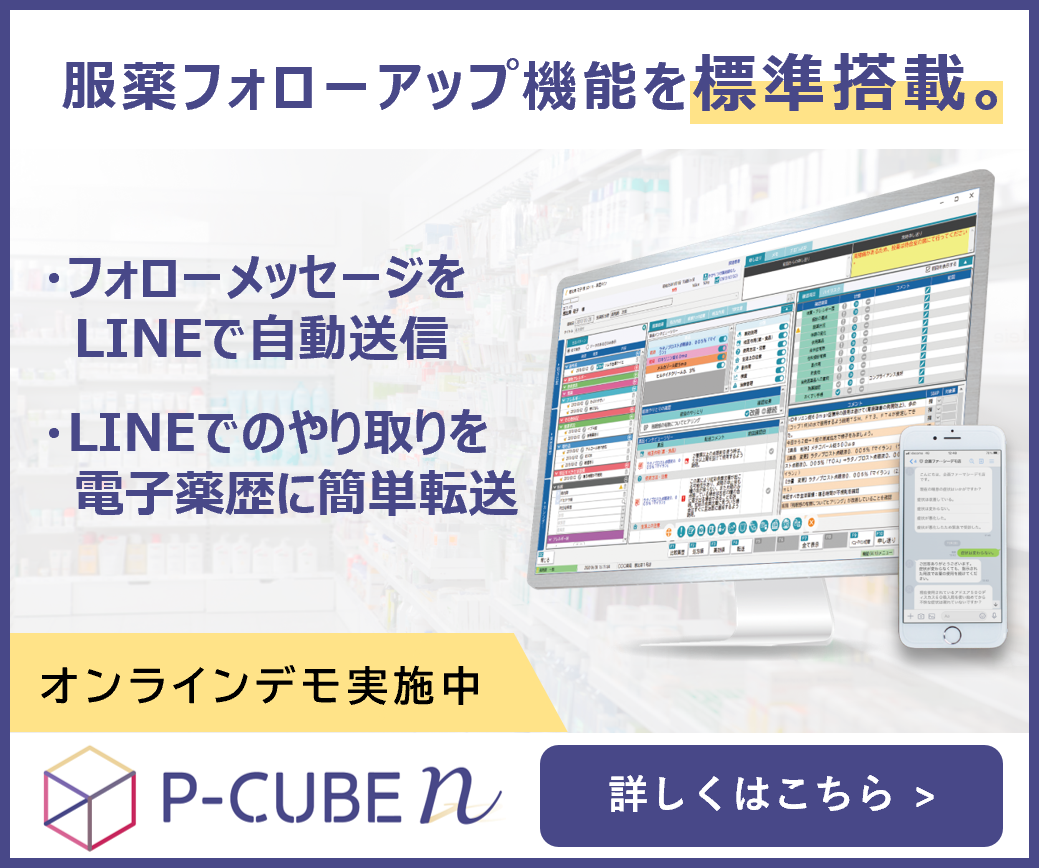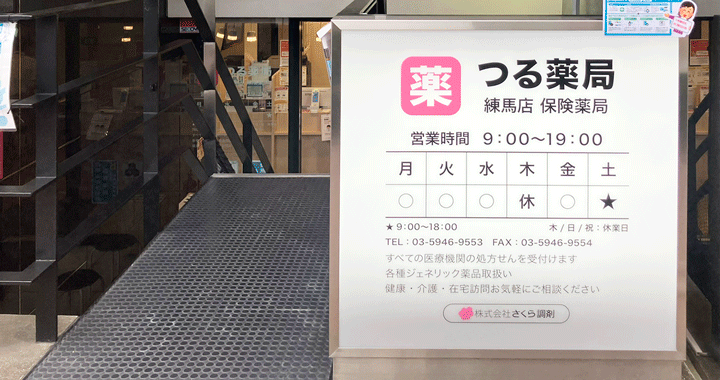
薬剤師コラム Vol.7
薬剤師の採用活動。採用側の本音と苦悩
薬剤師の転職活動は一般企業へ転職する方と大きく違う傾向があります。それは人材紹介会社を介してのエントリー割合が非常に多いということです。私も採用においては紹介会社とのお付き合いが20社ほどありました。また面接回数が1回という業界独特の慣習が存在しています。今回は薬局の採用担当者(担当役員)が求職者の何を見て採用という決断をくだしているのか、お伝えしたいと思います。
ご存じの通り、薬剤師の採用は難しい
私が薬局で採用担当を始めたころは、薬剤師を採用することが簡単にはできませんでした。そのため薬剤師が採用できない原因を探る必要があると感じ、紹介会社へアンケートを依頼しました。
そのアンケートの冒頭には「お世辞は一切不要です。私たちが足りていないことや問題と思われることについて、率直にお聞かせください。」と切実に訴えました。すると本当にお世辞なしの実直な意見をいただくことができました。教育制度、福利厚生、勤務体系について、詳しく説明することは心がけておりましたが、会社への帰属性が高い方ほど、キャリアパスやチーム医療で果たす役割、将来のVisionについて会社の考え方を知りたい傾向が強いことがわかってきました。
薬剤師に対するアピール方法や面接手法も変えることで採用活動は大幅に改善し、5,6社内定をいただいている方も私たちの企業を選んでいただけるようになり、内定者の辞退は限りなくゼロにすることができました。もう少し詳しくお伝えすると私ども薬局が求めている人材のみに内定を出すことができるようになり、紹介会社の中でも、優良企業としての位置づけをいただくまでに至ることができました。
採用担当者が何を求めているのか
それでは、売り手市場といわれる薬剤師の転職市場ですが、仮に買い手といわれる企業の方に第一選択権があるような場合、求職する薬剤師に対して何を求めたらよいのでしょうか?
当たり前のことですが、「企業人である前に医療人であること」です。しかし、薬剤師には「ヒポクラテスの誓い(医師)」や「ナイチンゲール誓詞(看護師)」のような哲学的思想がなく、そのため薬学部の教育で医療人になるための教育を積極的に受けられなかったという問題があります。
転職される方の多くは病気で入院したという経験も持たれていないと思います。薬剤師としての職責を全うし、生涯にわたり自己研鑽することで薬剤師の仕事に誇りを持ち、患者さんの立場も理解できるような医療人としての資質を持たれているかを探るのは難しいことです。会社の福利厚生、転勤の有無(範囲)、給与など含めて転職する理由をできる限り詳しく聞く中で医療人としての資質について判断するようにしていました。
縁があり、同じ職場で働いてくれるからには長く働いてほしいという強い思いが人事担当者であればあります。そして患者さんからの立場であっても、いつも同じ薬剤師が薬局に居てくれるだけで安心するという感覚はあると思います。短期で退職される方は「企業風土に馴染めない」という理由をあげられる方が多くいらしゃいます。つまり企業理念を理解することができず、合意に至らなかった方たちです。但し、企業理念は入社してから教育されていくものです。そのため、会社のホームページには求職者へ入社する前に同意していただきたい内容を掲載しています。それは会社が求める人物像や将来へ向けて会社が目指すべき方向性です。少なくともその内容を読まれているか、理解していただけているかについては選考基準に大きく影響してきます。